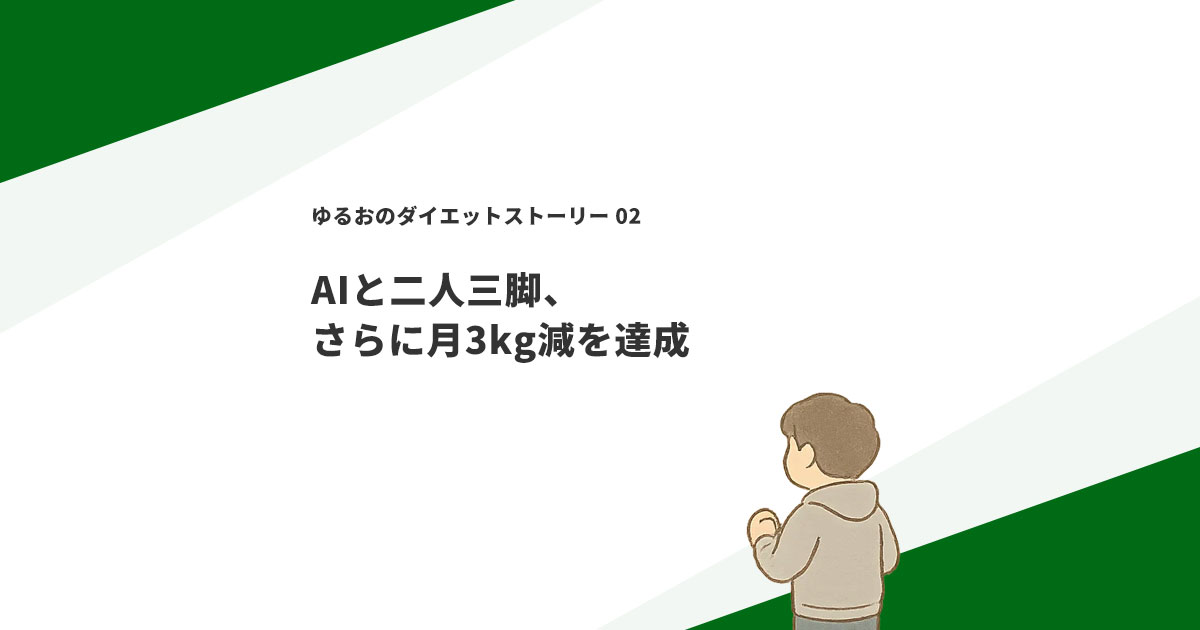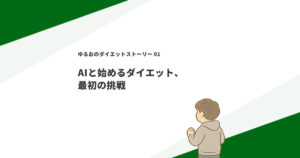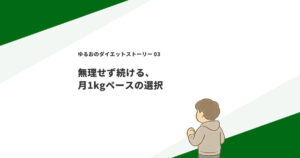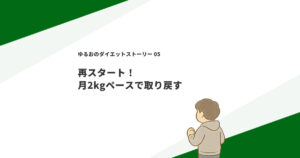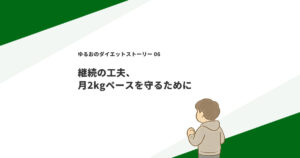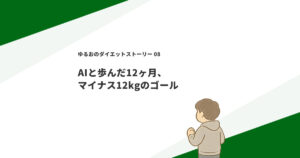「やればできるんだな」
5か月目でなんとか3kgを落としたとき、思わずそうつぶやいた。
けれど安心する余裕はなかった。
ここで止まればまたリバウンドする。
だから6か月目も、同じペースで続けるしかないと思った。
徒歩通勤、白米を少し減らす、AIへのざっくり報告。
やることは前月と変わらない。
それでも続けられたのは、いくつかの小さな気づきがあったからだ。
見られている感覚がモチベーションに
歩いていると、腕につけていたスマートウォッチが「ワークアウトを記録しますか?」と声をかけてくれる。
特に設定した覚えはないのに、勝手に気づいて知らせてくれる。
ただそれだけで「じゃあちゃんとやっておくか」という気持ちになる。
数字を細かく分析するほどマメではない。
それでも記録されているという事実は大きな支えになった。
AIに報告するのとあわせて、スマートウォッチのひと言が積み重なると、行動が少し背筋の伸びたものになる。
足の疲れとカロリーは別物だった
もう一つ大きかったのは靴のこと。
最初は「足がすごく疲れた=たくさんカロリーを消費した」と思っていた。
でも実際には、足の疲れと消費カロリーはほとんど関係がない。
体全体をしっかり動かして汗をかく疲れなら運動の成果になる。
けれど靴が合わずに足だけが疲れるのは、ただしんどいだけで消費は増えない。
それは努力でも成果でもなく、ただのロスだった。
そこでランニングシューズを見直した。
足に合う靴に替えただけで、同じ距離を歩いても余計に疲れることがなくなり、毎日を安定して続けられるようになった。
「足の疲れ=努力」ではなく、「続けられること=成果」。
この切り替えは、自分にとって大きな発見だった。
体重は日中でもかなり変化している
毎日体重計に乗ると、1kg前後は簡単に増えたり減ったりする。
塩分を摂りすぎた翌日は増え、汗を多くかいた翌日は減る。
以前はそのたびに落ち込み、気持ちが乱れていた。
AIは言った。
「日ごとではなく、1週間単位の平均で見ましょう」
実際にグラフにしてみると、日々の波の下に右肩下がりの流れがあった。
一日で増えた数字は、ただの水分や食事の重さ。
焦らずに流れを信じる方が確実に成果につながるとわかった。
ある日は前日より1kg増えてショックを受けた。
でも翌々日には元に戻っていた。
[数字に一喜一憂するより、流れを信じること]が大事だと腑に落ちた。
カロリー計算は「正確さ」が目的じゃない
献立をひとつずつ選んでカロリーを入力する。
そんな作業を毎日続けられる人はすごいと思うけれど、自分には無理だった。
そもそも食べ物の数字を正確に入れたとしても、その通りに吸収されるわけじゃない。
体質や体調によって消化や吸収率は違う。
同じメニューを食べても、すべてのカロリーが体に入るわけではない。
運動にしても同じだ。
ランニング30分=250kcalと書かれていても、その通りに消費できる保証はない。
姿勢やスピードの違いで数値は変わるし、長く続けると人間は自然に楽をしようとする。
同じ行動をしても、効率よく動くことで消費は少なくなる。
だから自分は、摂取は少し多めに、消費は少し少なめに見積もるようにした。
そうすれば、だいたいでも確実に赤字になるはずだから。
結局のところ、数字は正確さより「だいたいでいい」ことが分かってきた。
大切なのは続けられる仕組みであって、完璧な計算じゃない。
平均を基準に微調整するだけでいい
そこで自分がやったのは、大まかな平均をつかむこと。
例えば自分の場合、朝はだいたい300kcal前後、昼は500kcalくらい、晩ごはんは700kcal前後だった。
人によって数字は違うと思うけれど、毎日記録を続けていると自然に平均値は見えてくる。
そのうえでやり方は2通りあった。
ひとつは、入力する数字を調整する方法。
晩ごはんを「700kcal」とAIに報告しておき、
「今日は油が多かったから+100kcal」とか「煮物中心だから−100kcal」といった具合に足したり引いたりする。
もうひとつは、基準を700にしてご飯の量を調整する方法。
「今日は揚げ物だから、ご飯を少し減らして全体を700に収めよう」と考える。
食べる内容は変えずに、量でバランスをとるやり方だ。
このどちらかを選んでいれば、いちいち献立を入力する必要はない。
[大まかな平均+その日の微調整]で十分だった。
スマートウォッチに励まされ、靴を見直して無駄な疲れをなくし、
AIに教わった体重の見方で気持ちを安定させ、食事は平均と微調整で乗り切った。
結果は6か月目もマイナス3kg。
5か月目と合わせて2か月で6kgの減量に成功し、リバウンドを取り戻した。
結局やるのは自分だ。
でも、環境や見方を少し変えるだけで[続けやすさ]は大きく変わる。
そんな感覚がじんわり残った6か月目だった。